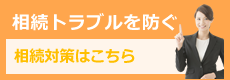遺言の基礎知識
遺言とは
人は自分の財産を自分の意思で自由に処分できます。
人の生前は、それは当然のことですし、人の死後もそれを可能にするのが、遺言(ゆいごん)の主な目的と言えるでしょう。
このように、遺言とは、人の意思や気持ちを、その人の死後も尊重するための制度です。
遺言に残したことは、人の死亡によって効力を生じます。
人が亡くなったあとは、本人にあらためて意思を確かめることはできないため、遺言に残せることはある程度限定しておかないと、残された人には判断が難しくなるおそれがあります。
そこで、遺言で本人が決められることは、法律で一定の事項に制限されています。
また、どのような人が遺言ができるか、どのような方法で行わなければならないか、など細かく決められています。
せっかく残した遺言が無駄にならないように、また、遺言者の意思を十分実現するためにも、遺言に関する法律について理解する必要があります。
遺言でできることは
遺言でできることは、法律で決められています。
決められているという意味は、決められた以外のことを遺言に残しても、法律上の効力が発生しないということです。
しかし、法律で決められたこと以外のことを遺言に残すのはその人の自由ですし、それを読んだ相続人が、その遺志を尊重するということはあるでしょう。
法律で決められたこと以外を遺言書に書いてはならないという訳ではありません。
では、法律上どのようなことを遺言で実現できるのでしょうか。
1.財産の処分方法
まず、遺言でできることには、当然ながら、財産の処分方法に関することがあります。
相続人の誰がどの財産を取得するか(遺産分割方法の指定)とか、相続人の誰がどれだけの割合で取得するか(相続分の指定)とか、特定の人に財産をあげる(遺贈)といったことです。
2.法律上の身分に関すること
つぎに、法律上の身分に関することがあります。
法律上の結婚をしないで生まれた子どもを父親が認知することや(その結果、その子どもは相続人となります)、残されていく未成年の子どもの後見人を指定したり、非行の激しい子どもを相続人から廃除したり、といったことができます。
3.遺言執行者の指定
その他重要なのは、遺言者は遺言執行者の指定ができるということです。
遺言の内容を確実に実現するためには、遺言の内容に従って遺産の管理や事務手続を行う遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)がいた方が望ましい場合があります。
遺言者は、自分が信頼のおける人に遺言の執行をして欲しいと考えるのは当然ですので、遺言執行者の指定が認められているのでしょう。
遺言はだれでもできるか
遺言は、どんな人でもできるという訳ではありません。
問題となるのは、次のようなケースです。
1.未成年者
未成年者が契約をする場合には、父母の同意が必要ということはよく知られています。
未成年者は判断能力が十分に育っていないので、それを保護する必要があるためです。
遺言も、契約と同じように、ある程度の判断能力が求められます。
しかし、遺言の場合は本人の意思の尊重をより優先させる必要があり、そのため契約よりもゆるい基準であり、満15歳になったら未成年者であっても、親の同意を得ることなく遺言ができます。
2.判断能力の落ちた人(認知症など)
未成年者ではなく成年だが、何らかの理由(病気や障がい)で判断能力が落ちているという場合はどうでしょうか。
われわれがよく遭遇する事案が、認知症の高齢者です。
認知症は、記憶力や判断能力が低下する疾患ですが、認知症の診断があるからといって、遺言ができないというわけではありません。
それは、認知症の程度次第ということになり、上記のように満15歳程度の判断能力があれば遺言が可能と思われます。
とはいえ、認知症のタイプも様々であり、ケースによっては、専門医の診察や判断も必要になるでしょう。
遺言はどのような方法でしなければならないか
自分なりに遺言を残そうと思い、パソコンに向かって遺言書をつくり、それをプリンターで打ち出して封筒に入れて保管していても、有効な遺言ではありません。
それは、この遺言書の作成方法が、法律に定められた方法に従っていないからです。
本人が死亡したあとに、遺言が本当に本人より作られたものかとか、遺言の内容が本当に本人の意思にそったものか、といった疑問や争いが生じることをできるだけ避けるために、法律では遺言の方法(方式)を細かく定めています。
方式には、大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
特別方式は、例えば死が間近に迫っているといったような特別な状況における遺言について、その方法を定めたものですが、それらについては、ここでは割愛します。
普通方式の遺言には、次の3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
1.自筆証書遺言
最も簡単に遺言をする方法が、この自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)です。
自筆証書遺言は、次の点を満たしていなければなりません。
①全てを自分で書くこと
自筆、自書であることが必要です。筆跡が重要ということです。ワープロや他人の代筆ではだめです。
②日付を記載すること
いつ遺言を作ったかということはのちのち重要な情報ですし、複数の遺言がなされた場合は、あとの遺言が有効になりますので、その前後の判断のためにも必要な情報です。日付は、年月日の日まで書かなければなりません。
③氏名を書くこと
この点、ペンネームや芸名であっても、本人が特定できれば有効と言われています。
④押印すること
実印、認印いずれでも構いません。指印は有効との判例もありますが、できれば避けた方がいいでしょう。
⑤決められた方法で訂正すること
書き損じた場合の訂正方法が細かく決められています。通常の訂正方法よりも厳格なので注意が必要です。自信がない場合は、書き直した方がいいかもしれません。
自筆証書遺言は、自分1人で、費用をかけずに作成することができますが、第三者の関与がないところで作成されるため、遺産をめぐる争いが生じたような場合には、他の方法の遺言に比べ、確実性に欠けると思われます。
2.公正証書遺言
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証人(こうしょうにん)に関与してもらい、証人2人以上の立ち会いのもと遺言書を作成し、作成した遺言書の原本を公証役場(こうしょうやくば)で保管してもらうものです。
公証人という法律に詳しい人が関与し、遺言書も保管してもらえるので、遺言の内容を実現するためには、最も確実な方法と言えます。
ただし、その分、公証人に報酬を支払わなければなりません。
また、証人を頼まなければなりません。
証人は誰でもなれるというわけではなく、利害関係のある一定の範囲の人(例えば本人の相続人など)は、証人になることを認められていません。
遺言の作成には、原則として、公証役場に出向いて手続をしなければなりませんが、本人が病気で動けない場合などは、公証人が自宅や病院に出張してくれます。
自筆証書遺言に比べ手間と費用はかかりますが、遺言としては確実な方法であるため、遺言の相談を受けたときは、われわれも原則として公正証書遺言を勧めています。
また、公正証書遺言作成の依頼を受けたときに適当な証人がいない場合、われわれが証人を引き受けるということもあります。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)は、遺言書自体は本人が1人で作成し封筒に入れて封印しますが、その封筒を公証人と証人2人以上の前に提出して、これが自分の遺言書であることなどを述べてそれを封筒に記載し、さらに公証人、本人、証人が署名押印することにより成立するものです。
公証人等が関与することで、遺言書の存在が第三者に明らかになりますが、公正証書遺言のように遺言の内容にまでは関与しないので、内容を秘密にしておくことができます。
公証役場は、遺言書の保管まではしてくれません。
実務上は、経験することがきわめて乏しい遺言です。
遺言を取消したり変更するには
遺言は、本人の意思の実現のためにあるものですから、一度した遺言も本人が自由に取消したり、内容を変更することができます。
その方法としては、さらに遺言をすることによって取消・変更をします。あとになされた遺言の方が有効ということになります。
また、あらたな遺言によらずに遺言の内容が取消・変更されたことになる場合もあります。
例えば、自宅の不動産についてはAさんにあげると遺言したあとに、生前にそれをBさんに売却したような場合、自宅の不動産をAさんにあげるという内容は実現しようがないので、遺言のその部分については、取り消されたものとなります。
あくまで、本人の意思が一番尊重されるということです。
遺言書を発見したら(検認について)
遺言者が死亡し、その後本人のものと思われる遺言書が見つかった場合はどうしたらいいでしょうか。その場で封を開け、内容を確認してもよいでしょうか。
また、生前から遺言書の保管を頼まれていた場合、遺言者が死亡したらその遺言書をどうしたらよいでしょうか。
このような場合、遺言書の封を開けず、なるべく早めに家庭裁判所に提出して、検認(けんにん)という手続をとらなければなりません。
検認とは、家庭裁判所から相続人に呼出がなされ、相続人の立ち会いのもと、遺言書を開封したり遺言書の内容を確認したりする手続です。
それにより、遺言書に対し家庭裁判所が検認を行ったという証明が付けられます。
この手続により、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防ぐことを目的としています。
ただし、検認を受けたからといって、遺言の内容が有効だとの判断を受けたという訳ではありません。
なお、公正証書遺言だけは、検認の手続は必要ありません。
遺言執行者とは
人が遺言を残したとしても、たとえば、その人が亡くなったあと相続人が遺言をまったく無視してしまったら、その人の遺志の実現は不可能になってしまいます。
そこで、遺言を残した人の遺志を確実に実現するために、遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)という制度があります。
遺言執行者は、相続財産を適切に管理し、遺言の内容にしたがって財産の引継を行うなど、遺言に書かれた内容を実現する仕事をします。
遺言執行者は、遺言者が遺言の中であらかじめ指定しておくことができます。
遺言執行者は遺言者のために仕事をする人ですから、遺言者が信頼できる人を決めておくことができるわけです。
遺言者は、自分で遺言執行者を決めることができなくても、遺言で第三者に遺言執行者を指定することを委託しておくこともできます。
また、遺言で遺言執行者が指定されていなかったとしても、相続人などが遺言執行者を必要と考えた場合は、家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選んでもらうことができます。
われわれ司法書士も頼まれて遺言執行者になることがあります。
遺言執行者の資格に制限はありませんが、遺言の内容を実行するために法律の専門的な知識が必要になるような場合には、司法書士や弁護士の法律専門家に任せておく方が安心です。
遺言には従わなければならないか(遺留分について)
人は、自分の財産を自由に処分できますので、生前に誰かに贈与したり、遺言で特定の人に与えることも自由です。
では、亡くなった人が遺言を残していたために、ある相続人が相続財産をまったく引き継ぐことができなかったり、また、わずかしか引き継げなかったような場合、その相続人はそれを甘んじて受け入れなければならないのでしょうか。
そのような場合に相続人を保護する制度として、遺留分(いりゅうぶん)があります。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に相続財産の中から最低限の取り分を保障する制度です。
もし、被相続人による生前の贈与や遺言を受け入れられないと考えるのであれば、遺留分の請求をすることにより決められた割合まで相続財産を取得できる場合があります。
遺言を残しておくべきケースとトラブル例
-
2017年03月17日未分類
-
2017年03月17日未分類
-
2016年11月15日未分類
-
2016年10月24日未分類
-
2016年09月07日未分類